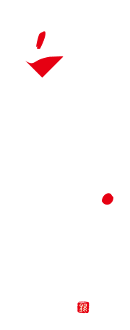私と仕事

たった2頭の牛からはじまった挑戦
川井さんの祖父の代は、棚田でお米を作る農家さんで、農作業用にあかうしを2〜3頭飼っていたそう。 この嶺北地域では、古くから農作業に牛を使う風習があったといいます。川井さんがまだ生まれる前、山口の学校からUターンで戻ってきた20代の父親が、畜産業に本格的に着手したことから、川井畜産の歴史は始まりました。当初はホルスタインをメインに30頭ほど飼っていたのですが、オイルショックにより価格が暴落。この時、農耕用に飼っていたあかうしが食用に転換したこともあ り、あかうしの生産に転換したそうです。

逆境を乗りこえた父の信念
当初は子牛を育てる「肥育経営」から始めましたが、少しでも利幅を増やすため、試行錯誤を重ねながら繁殖も行っていきました。 順調にあかうしが増えてきた頃、今度は牛肉輸入自由化が起こります。赤牛と外国産の牛肉の区別がつきづらかったこともあり、価格が激減。ただ、 繁殖から飼育、販売までを行う「一貫経営」をしていたこともあり、なんとか乗り切れたそう。その頃まわりでは、あかうしではなく、サシが入っている黒牛に転換する農家もあったそうですが「いつかきっとあかうしの美味しさが評価される時がくる」と父親が固く信じ、あかうしの生産を続けてきました。

度重なる困難に打ち克つ信頼
3代目の規共さんが宮崎の大学を卒業して帰郷した頃には100頭ほどのあかうしを生産するまでになっていました。牛に囲まれた暮らしをしている中、今度はBSE問題が起こりました。 国産牛にも影響が及び、価格の下落や販売不振に陥ります。ただ、この時も一貫経営だったことが功を奏して乗り切れたといいます。オイルショック、牛肉輸入自由化、BSE問題と、親の代から何度も困難に直面しながらも、ずっと牛を守り続けてこられたのは、川井さんたち一家の真摯な姿に寄せられた信頼があったからなのでしょう。

地道な努力で得たたしかな評価
川井さんの育てた土佐あかうしは、ほどよく脂がのっていて、赤みのふくよかな旨みがしっかりと味わえるのが特徴です。食の安心・安全にこだわり、牛たちのエサには国産稲藁を選んでいます。現在200頭にまで増えた牛たちのエサやりにかける時間は、1回約2時間。朝と晩のあいだも、エサの準備で大忙しです。子牛には、自らの手でミルクをあげるそうです。そうして丁寧に手をかけてきた努力が評価され、県内の品評会で3度も最優秀賞を受賞するほど、信頼と評価を確かなものにしています。苦難があっても、実直に目の前の問題や課題に取り組んできた川井さん一家だからこそ、得られたものではないでしょうか。
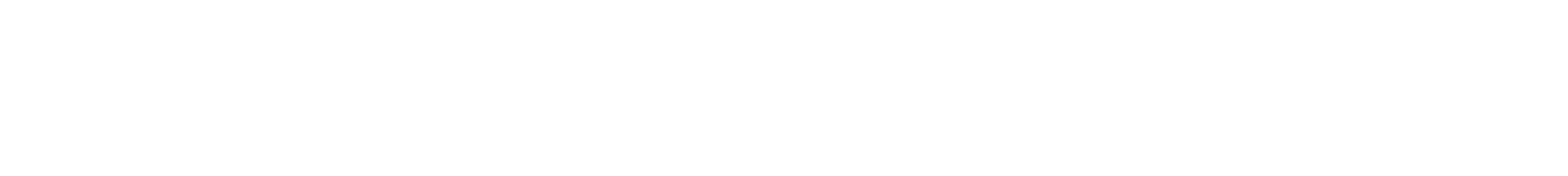










 高知で働く
高知で働く 高知の魅力
高知の魅力 サイト情報
サイト情報