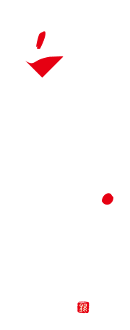私と仕事

ふるさとを求めて、高知へ
前職でのハードワークで心身ともに疲弊し、いつしか生まれ育った故郷のような田舎暮らしを求めていたという和田さん。転職を考えた当時、幼少期を過ごした榛東村の家は両親によって売却され、帰る場所がなかったそう。そこで地元群馬以外の田舎でのチャレンジを決意し、「日本一人口が少ない村」だという大川村への赴任を決意したものの、農業は未経験、そもそも自分に田舎暮らしができるのか、行った先で役にたてるのか…当初は不安でいっぱいだったといいます。

前例もなく決まった役割もない村で、仕事をつくる
和田さんが赴任した当時、大川村では協力隊の受け入れ前例がない状態でした。そのため、まずは村の方たちに顔を覚えてもらい、どんな仕事が必要とされているのかを知る事からスタート。村の担当職員や集落支援員とともに挨拶まわりをしたり、地域の活動に同行して村の方たちと触れ合っていく中で、どんどん知り合いが増えていきました。対話を重ねる中で、自分に何ができるのか、どんな役割を期待されているのかを感じられるようになっていきました。

村全体で、何もできない自分を支えてくれた
1ヶ月ほどすると、農家さんからお手伝いを頼まれたり、住民の方と共に草刈りをしたりとさまざまな所から声がかかるようになり、2〜3ヶ月目にはすっかり地域にとけこめていたそう。実は和田さん、群馬の村出身ですが、農業に携わった経験はなく、技術的なことや人との付き合い方まで一からいろんな方に教えていただいたといいます。ほうれん草農家や花農家で基本的な研修をうける等、どんな仕事をするにしてもサポートする人がいてくれた大川村だからできた事かもしれません。農業未経験者でも、安心して赴任できそうですね。

地産地消をかなえるシステムづくり
地域の方のお手伝いをしながら、和田さんが地域おこし協力隊として主に活動していたのが、村の給食センターの立ち上げと運営サポート。もともと嶺北エリアには給食センターがひとつあったのですが、村の野菜をつかって地産地消し、経済をまわせる仕組みを作りたいという思いで立ち上がりました。住民の方に協力をあおぐための説明や食の調査を行い、行政と地域住民とのパイプ役を担うようになりました。

村のため、隣にいる誰かのために働く
村で野菜栽培のお手伝いをしたり、給食センターや直売所でスタッフとして働いたりしながら、どうしたらこの村の野菜を多く買い上げ、より豊かな経済システムを作れるのだろうかという事を考えながら活動を続けた和田さん。大川村では、決まりきった仕事はありません。協力隊員の希望をききながら、そして何より地域住民の方が何を必要としているのかを考えながら、仕事をつくっていくというスタンスです。農業枠での採用といっても、ひたすら農作業をしているわけではなく、基本的には行政と住民をつなぐ役割がなによりも大切なのだそう。「農業という切り口をもちながら、1つの仕事だけでなく幅広く地域に根ざしていける人と働きたい」と語ってくれました。
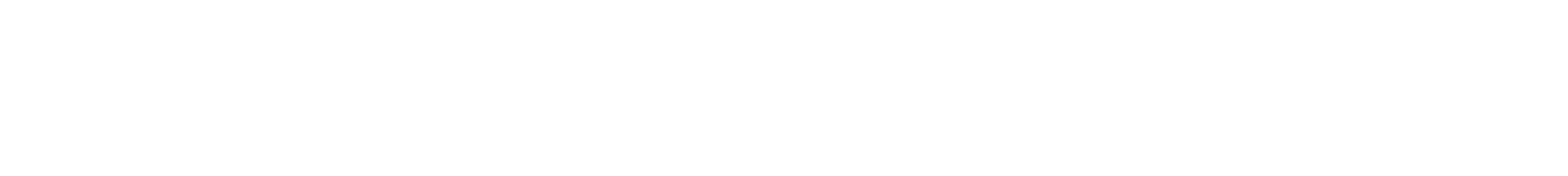











 高知で働く
高知で働く 高知の魅力
高知の魅力 サイト情報
サイト情報